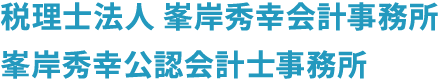企業の税務 corporate-tax
- 企業の税務
- 2022.01.06
従業員を外注先に変えると節税になるという甘い話にご注意を

はじめに
従業員を外注先に変えると節税になると聞いたのでやりたい、というご相談を、未だにいただくことがあります。今はひと頃ほどではないと思いますが、それでも、こういう話をあたかも節税スキームのように吹聴する人がまだいるのでしょう。
実際、従業員に支払う給与と、外注先に支払う報酬とでは、前者は消費税が課されない取引である一方、後者は消費税が課される取引ですから、後者の方が支払う側の企業にとっては資金繰り的に有利であるといえなくはありません。同じ110万円を給与として支払ってもその企業の消費税の計算から差し引ける金額は何もありませんが、報酬として支払えば10万円を差し引くことができ、消費税の納税額が10万円減ります。一方、それを受け取る側が消費税の課税事業者でない場合には、給与で受け取ろうと報酬で受け取ろうと手元に残る金額が変わらないように(一見して)思われますから、お互いにWin-Winだ、と錯覚するのも無理からぬところです。
しかし、お仕事をお願いする人との間で「雇用」という関係を選ぶのか、「請負」や「委任」という関係を選ぶのかということを、節税を動機にして決めるのは実に筋が悪いことです。関係を変えるということは決して紙切れ一枚で済むことではなく、文字通りにお互いの関わり方が変わるということなのであり、それが自社のビジネスと従業員本人にとっていいことなのかどうかをまず考えるべきでしょう。「関わり方は変えたくないけど課税関係は変えたい」という願望は残念ながら叶いません。実際に関わり方が変わるからこそ課税関係が変わるのです。
今後、ある理由でこのようなご相談をいただくことは減っていくだろうと思いますが、この古くて新しい論点について一度整理しておきたいと思います。
給与と報酬の違い
この「スキーム」の要点は、給与には消費税がかからない、報酬には消費税がかかる、という課税関係の差にあります。そこでまず、給与と報酬の違いについて確認しておきましょう。
給与とは、それを受け取る人にとって給与所得になるものだと考えればよく、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいい、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならないと解されています。これに対して、報酬とは、それを受け取る人にとって事業所得になるものだと考えればよく、事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいいます(注1)。
大雑把にいえば、税務上、給与と報酬とは、以下の2つの視点で区別できると理解しておけばイメージが湧くのではないでしょうか。
・支払う者と受け取る者の間に支配従属・指揮命令のような関係があるのは給与で、対等なのが報酬。
・支払う者がビジネス上の危険(赤字リスク)を引き受けているのが給与で、受け取る者がビジネス上の危険(赤字リスク)を引き受けているのが報酬。
給与を受け取る人というのは、使用者からいわれたとおりに仕事をしなければならず、仕事をどのように・どこで・いつするのかということについての裁量は小さいですが、反面、仕事が遅かったり完成しなくてもお金はもらえますし、全く働けなくてももらえるお金がゼロになるだけでマイナスになったりしません。
逆に、報酬を受け取る人は、依頼された仕事をどのように・どこで・いつするかということについて裁量がある反面、仕事をしなければお金はもらえず、傷病などによって働けなくなりお金をもらえなくなったとしても事務所家賃や仕事道具などの経費はなくなりませんので、赤字に陥る危険を負っています。
従業員を外注先に変える、ということは、つまり、仕事について広範な裁量を与える代わりに仕事上の経費や危険を本人に負担させるということです。もしそのことをきちんと理解していれば、従業員から外注先に立場が変わる側は、とても今までと同じ金額では仕事ができないでしょう。企業の側も、今までのようにコントロールがきかなくなることに心の準備が必要です。
従業員を外注先に変えるということは、そういったことをしっかり考えて決める必要がある話なのです。決して節税という視点だけで考えるべき話でないことがお判りいただけると思います。
なお、金銭を支払う側と受け取る側の契約関係が税法以前にどう判断されるかということは、税務上の給与と報酬の該当性の判断に致命的な影響を与えません。民法上の雇用契約に当たらないからといって、税務上の「雇用契約又はこれに類する原因」に当たらないとは限らないことにご注意ください。
給与への該当性の具体的な判断基準
課税実務の現場では、授受された金銭が給与であるのか報酬であるのかということは大変微妙で判断の難しい問題です。その具体的な判断基準について、最近、少し踏み込んだ判断をした裁判例(注2)があります。
この裁判では、塗装工事業の会社が従業員から外注先に変えた者に対する支払いが給与に当たるのか、報酬に当たるのかが争われました。その判断にあたり、裁判所は消費税法基本通達1-1-1が給与該当性の判断に当たっても参考になるとしました。この通達は以下のような基準を示しています。
(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
(2)~(4)は先に述べたことでご理解いただけると思いますが、(1)の意味するところは、お金をもらう本人が仕事できなくなった際に代わりの人員を誰が手当てしなければならないか、ということです。外注先の立場であれば、ひとたび請け負った仕事に請け負った本人が行けなくなれば、依頼主に対して代わりの人員を手当てする責任を負うのも本人だろう、ということです。そうでないのなら給与であると判断される可能性が高まることになります。
やがて廃れる?この「スキーム」
従業員を外注先に変えることで消費税を「節税」するというこの「スキーム」ですが、おそらく、今後そのような視点で議論されることは少なくなってくると思います。その原因は、来年10月から開始するインボイス制度です。
というのも、この「スキーム」のミソは、報酬を支払う企業の側はその報酬に係る消費税を差し引きて納税額を減らせる、しかし、受け取る外注先の側は消費税の免税事業者でありこれを納めなくていい、というところにありました。
しかし、インボイス制度の下では、適格請求書発行事業者が発行した適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となります。適格請求書発行事業者には、課税事業者でなければ登録することができません。要するに、報酬を支払う企業の側でその報酬に係る消費税を差し引きたければ、その相手方の外注先が消費税を納めていることが条件になるのです。
そうなると、企業の側は今まで給与だった金額を変えずに報酬に変え、外注先に支払って10%相当額だけ税金を減らして得をするという目的を達成するためには、その外注先に10%相当額を納税してもらって今までよりも手取りを減らしてもらわなければなりません。これでは従業員の側が外注先になることを了承しないでしょう。
インボイス制度が始まった後も6年間は免税事業者からの仕入れに係る仕入税額控除の経過措置がありますので(注3)、直ちに全額控除不能になるわけではないのですが、しかし旨味が減ることは間違いなく、したがってこの「スキーム」は徐々に下火になるだろうと思います。
おわりに
このお話に限らず、事実関係の現状を変えずに契約書だけをコチョコチョと弄って課税関係を変えて節税する、という発想には、根本的な無理がある場合がほとんどです。また、この手のお話しには必ずといっていいほど「その人は税務調査を受けても平気だったといっていた」という伝聞がセットになっています。しかし、税務調査で問題提起されるかどうか、あるいは更正処分に至るかどうかということは、実際の事実関係に依存するのであって、そこのところを細かく聞きこんでみない限りは「平気だった」のかどうかは判断できません。くれぐれもご注意ください。
税理士法人峯岸秀幸会計事務所では、セカンドオピニオンを含め、税に関するご相談を承っております。是非お気軽にご相談ください。
(公認会計士・税理士 峯岸 秀幸)
(注1)最判二小昭和56年4月24日民集35巻3号672頁参照。
(注2)東京地判令和3年2月26日TAINS Z888-2352参照。
(注3)詳細は日本税理士会連合会ウェブサイト(2022年1月6日最終確認)を参照。
***本記事のタイトルで使用している写真はAya Hirakawaさんの作品です。